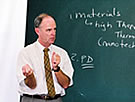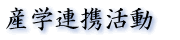
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成26年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成26年度分)
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成27年1月22日(木) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
株式会社日立製作所 日立研究所 電力流通研究部
六戸 敏昭 氏 |
| 講演題目 |
「ドライエアGISの現状技術とSF6代替絶縁技術の展望」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
|
【概要】
環境意識の高まりを背景に,温室効果ガスを使用しないガス絶縁開閉装置(GIS)のニーズが顕在化してきた。SF6代替ガスとして現在ではドライエアが主流であり,70kV級GISまで製品化が進み,日本が世界をリードしている分野のひとつである。
ドライエアとSF6ガスの絶縁特性の違いがなぜ生じるかの基礎的な話から,GIS開発時の技術課題と対応について説明いただくと共に,最近の新ガスに関する動向についてご紹介いただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成26年12月17日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
伊藤 正治 氏 |
| 講演題目 |
「洋上風力発電技術の動向」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生38名 教職員6名 学外17名 計61名 |
|
【概要】
近年,我が国においても,着床式洋上風力発電や浮体式洋上風力発電の実証研究が進められ,各地で洋上風力発電ウインドファームの検討が進められている。しかしながら,現状は洋上風力発電の本格的な導入に向けては,更なる技術開発や支援策が必要とされている。
本講演では,これまでの実証研究で明らかになった課題や洋上風車,基礎,設置,維持管理などの項目について,先行している欧州との比較を行うことで,わが国における洋上風力発電の問題点を明らかにしていただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成26年12月3日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
国立大学法人東京大学 大学院新領域創成科学研究科
太田 豊 氏 |
| 講演題目 |
「電動自動車を利用したスマートグリッドの応用例と研究課題」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生41名 教職員5名 学外15名 計61名 |
|
【概要】
電動自動車の電力貯蔵/電力変換/情報通信の機能は,快適な走行環境を提供するだけではなく,スマートグリッドのキーテクノロジーとしての期待が集められている。
この講演では,電動自動車と電力系統の今後の関わりを展望するとともに,国内外の先進的な応用事例や技術動向を紹介いただいた。また,スマートグリッド応用のバックグラウンドにある電力系統,電力貯蔵,自動車システムに関する技術について,研究事例を示しながら解説いただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成26年10月29日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
国立大学法人東京大学
日髙 邦彦 教授 |
| 講演題目 |
「高電圧・電力分野の研究開発動向と展望」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生41名 教職員6名 学外36名 計83名 |
|
【概要】
電力に対する世界の需要は右肩上がりで増加しており,これに対応するため電力分野への投資額はこれから数十年以上,毎年70兆円規模と見込まれている。一方,震災以降における日本の対応は,2030年のベストエネルギーミックスの方向性を模索すると共に,「50Hzと60Hzの連系強化」および「再生可能エネルギーの大量導入への対応」が急務となっている。世界の中の日本として,中長期的にどのように高電圧・電力分野の技術開発を進めるべきか,特に,基礎技術開発,新製品開発,および,技術戦略に関し,最近の動向と今後の課題,展望について講演いただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成25年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成25年度分)
 vol.4 vol.4
九州大学・九州工業大学 寄附講座 (九州電力株式会社)
合同シンポジウム(第5回)
「有機絶縁材料の現状技術と今後の展望」
| 日 時 |
平成26年3月14日(金) 13:00 - 16:45 |
| 場 所 |
電気ビル 共創館 3階 共創館カンファレンスA(大会議室) |
| 主 催 |
九州大学「電気エネルギー環境工学講座」・九州工業大学「電力系統制御工学講座」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter, IEEE Fukuoka Section
|
| 参加者 |
学生4名 教職員10名 学外60名 計74名 |
|
【プログラム】
| 13:00-13:10 |
ご挨拶 |
|
 九州電力株式会社 九州電力株式会社 |
| 13:10-14:10 |
基調講演 |
|
『日本における有機絶縁材料の歩みと技術動向 』 |
|
 一般財団法人電力中央研究所 電力技術研究所 首席研究員 岡本 達希 一般財団法人電力中央研究所 電力技術研究所 首席研究員 岡本 達希 |
| 14:10-16:40 |
パネルディスカッション |
|
|
進行: 国立大学法人 九州工業大学 教授 匹田 政幸 |
|
1) 情報提供 |
|
| |
『各種ポリマーがいし・がい管の適用状況』 |
| |
 日本ガイシ株式会社 電力技術研究所 マネージャー 近藤 高徳 日本ガイシ株式会社 電力技術研究所 マネージャー 近藤 高徳 |
| |
『鉄道電力設備におけるポリマーがいし/がい管の適用状況』 |
| |
 東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本研究開発センター 東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本研究開発センター |
| |
テクニカルセンター 上席研究員 山本 浩志 |
| |
『避雷器へのポリマー材料の適用状況』 |
| |
 国立大学法人 九州工業大学 客員教授 石辺 信治 国立大学法人 九州工業大学 客員教授 石辺 信治 |
|
− 休憩 (14:55-15:10) − |
|
| |
『超電導電力応用における絶縁技術の現状』 |
| |
 国立大学法人 名古屋大学 教授 早川 直樹 国立大学法人 名古屋大学 教授 早川 直樹 |
| |
『超電導電磁石応用における絶縁技術の現状』 |
| |
 国立大学法人 九州大学 准教授 東川 甲平 国立大学法人 九州大学 准教授 東川 甲平 |
| |
『有機絶縁材料におけるナノテク研究動向』 |
| |
 国立大学法人 九州工業大学 准教授 小迫 雅裕 国立大学法人 九州工業大学 准教授 小迫 雅裕 |
|
2) ディスカッション |
|
| 16:40-16:45 |
纏め・閉会挨拶 |
|
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成26年1月15日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
渡邊 重信 氏 |
| 講演題目 |
「我が国における再生エネルギーとNEDOの取組みについて」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生31名 教職員4名 学外38名 計73名 |
|
【概要】
2012年7月,再生可能エネルギー由来の電気についての固定価格買取制度(Feed-in-Tariff)が導入されて以来,太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入が大きく進展しており,その大量導入が現実のものとなってきました。その一方で,コストの問題や系統制約などの課題が顕在化しています。
本講演では,我が国における再生可能エネルギー導入の現状と課題,課題解決に向けたNEDOの取組みを紹介いただきました。また,最近,関心が高まっている洋上風力発電について,NEDOによる実証事業や関連する技術開発について紹介いただきました。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成25年12月11日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
関西電力株式会社
花田 敏城 氏 |
| 講演題目 |
「関西電力におけるスマートグリッドへの取組み」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生33名 教職員5名 学外42名 計80名 |
|
【概要】
低炭素社会の実現に向け,従来から太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの活用拡大が求められてきたが,東日本大震災以降は一層の導入促進が叫ばれている。日本では2009年の政府方針で,2020年に2800万kW,2030年に5300万kWの太陽光発電の導入目標が定められているが,2012年に風力発電等も含めた固定価格買取制度(FIT)が導入され,更に進展する見込みである。
関西電力殿では化石燃料に依存しない低炭素電源として原子力発電を率先導入するとともに,太陽光発電や風力発電の技術開発に努めてきた。最近では日本の電力会社に先駆けてのメガソーラー発電所の建設や,関係会社によるウィンドファーム開発等,自ら再生可能エネルギーを活用する取組みをしているが,今後,FITを活用して大量の再生可能エネルギーが電力系統へ接続されることが予想され,その際にも安定供給が継続できるように様々な研究開発を実施している。
本講演では,特に太陽光発電の大量導入に向けた対策技術として,太陽光の出力予測,二次電池による需給制御システム,スマートメーター,配電自動化システム,エネルギーマネジメントシステム等の開発,実証,導入によるスマートグリッドの取組み状況について紹介いただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成25年10月30日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 百周年中村記念館 多目的ホール |
| 講演者 |
株式会社明電舎
野口 卓孝 氏 |
| 講演題目 |
「電気二重層キャパシタ(蓄電デバイス)の新技術」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生32名 教職員8名 学外22名 計62名 |
|
【概要】
電気二重層キャパシタは,電気エネルギーを一時的に貯蔵,放出できるデバイスとして,一般的な二次電池と比較して低抵抗,長寿命といった優れた特長を有する反面,エネルギー密度が低く,大容量化が大きな課題となっています。エネルギー密度を大幅に向上することができれば,電気自動車をはじめとする車載への適用など,更なるアプリケーションの拡大が可能となります。
このほど株式会社明電舎殿にて,集電体に三次元アルミニウム多孔体,活物質にカーボンナノチューブ,電解液に不燃性のイオン液体を適用することで,従来の電気二重層キャパシタと比較して,体積エネルギー密度は約3倍,かつ広い温度範囲での作動が実現されました。
本講演では,同社のキャパシタ事業と新技術を中心にご紹介頂きました。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成24年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成24年度分)
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成25年2月18日(月) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
東芝三菱電機産業システム株式会社
堤 理一郎 氏 |
| 講演題目 |
「回転電気機械:電動機・発電機」 −種類・歴史・用途・技術・保守・診断の概要と技術動向−
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生19名 教職員6名 学外36名 計61名 |
|
【概要】
エネルギー変換機器の一種である電動機および発電機(回転電気機械)は,幅広く産業界に活用されておりその種類も多岐に及ぶことから,本講演では,大形から小形までの電動機・発電機の種類を基礎的な視点で幅広くご紹介していただいた。また,その中で,生活の場や書籍などでは日頃なかなか親しむことが無い,事業用発電・鉄鋼・非鉄金属・石油化学・紙パルプ・荷役などの業界で活用される大形の電動機・発電機を中心に,歴史・用途・技術・保守・診断などについて基本的な内容と技術動向をご紹介いただいた。
電動機・発電機は製造業などの第二次産業に携わる技術者にとって,様々な場面で関連する機器の一つであり,中小形電動機・発電機を取り扱っておられる技術者にとっても大いに参考にしていただけるご講演であった。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成25年1月22日(火) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
三菱電機株式会社 電力・産業システム事業本部
伊藤 弘基 氏 |
| 講演題目 |
「電力機器に関するCIGREの活動状況と電力技術者への期待」
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生33名 教職員8名 学外17名 計58名 |
|
【概要】
CIGRE(国際大電力システム会議)は,第一次世界大戦後,送電網の多国間連系が開始されたのに伴い,電力関連技術および電力供給事業に関して,国際的に中立な立場で意見交換する場と,IEC(国際電気標準会議)における電力分野の国際標準化の根拠となる技術背景を調査する組織が必要となり,1921年に設立された。現在でも,CIGREは変圧器,開閉機器,変電所,保護リレー,系統計画,分散電源,電力通信など16の調査専門会を組織して,送変電技術に関する諸問題,なかでも新技術の利害得失を討議するのが大きな使命となっており,国際的な実績調査・意見交換に基づく有望な技術を熟成・国際標準化を推進している。
本講演では,本年8月に欧米以外からは初めて本部委員長に就任された伊藤様をお招きし,CIGREの歴史的役割,最近の調査活動の具体的事例として,遮断器の国際信頼性調査,真空遮断器の変電適用時の課題調査,UHV(超超高圧)技術仕様および開閉責務調査,開閉極位相制御の実態調査などの概要に加えて,再生可能エネルギーの導入拡大,DC送電など最近の調査活動を解説頂いた。また,本部委員長および主査(議長)として臨んだ国際会議における各国電力関係者との議論を通じた体験を紹介頂き,国際標準化活動の重要性についてもお伝えして頂いた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成24年11月8日(木) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
九州電力株式会社
橋本 洋助 氏
長嶺 茂 氏 |
| 講演題目 |
「配電システムの運転と保全に関する取り組みと今後の方向性」
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生18名 教職員6名 学外55名 計79名 |
|
【概要】
配電系統においては,今後,設備の高経年化の進展とともに,太陽光などの分散型エネルギーの大量導入が想定されることから,これまでの「需要増に対し設備を拡充する」といった対応とは異なる設備の運用管理が必要となってくる。それに対応するためには,配電設備に対する4つの業務プロセス(計画,建設,運転,保全)の中で,運転と保全が重要となってくる。具体的には,設備の運転技術と保全技術の高度化によって,用品機材の長寿命化や設備劣化に起因する事故の予知・未然防止の技術を確立することで,設備を限界まで使いながら,高品質な電気を供給することが求められる。
今回の講演会では,配電システムの運転と保全に関する技術について,最近のトピックスを交えながら,九州電力殿の現在の取り組み状況と今後の方向性についてご紹介して頂いた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成24年7月6日(金) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
東芝産業機器製造株式会社
東山 雅一 氏 |
| 講演題目 |
「モールド変圧器を含む電力機器の最新技術動向および新技術開発」
−社会インフラを支える電気機器の開発と製造−
|
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
| 参加者 |
学生13名 教職員3名 学外37名 計53名 |
|
【概要】
近年の社会システムの高度情報化に伴い,電力の安定供給が強く求められている。この電力供給を支える社会インフラのひとつが,電圧変換を担う変圧器で,プラント・機器への電力安定供給,信頼性維持のために重要な役割を果たしている。
変圧器は,油入・SF6ガス絶縁・シリコーン乾式・モールド変圧器などに大別されるが,今回は,これら各種変圧器の用途・特徴などをご紹介して頂くとともに,モールド変圧器を例として産学連携活動による技術開発動向を含む種々の技術動向についてもご紹介して頂いた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成23年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成23年度分)
 vol.6 vol.6
九州大学 寄附講座(九州電力株式会社)「電気エネルギー環境工学講座」
九州工業大学 寄附講座 (九州電力株式会社)「電力系統制御工学講座」
合同シンポジウム 「次世代電力システム・電力機器の最新動向」
| 日 時 |
平成24年3月5日(月) 13:00 - 17:20 |
| 場 所 |
九州電力株式会社本店(電気ビル本館) B2F 7号会議室 |
| 主 催 |
九州大学 寄附講座(九州電力株式会社)「電気エネルギー環境工学講座」
九州工業大学工学部 寄附講座 (九州電力株式会社) 「電力系統制御工学講座」 |
| 共 催 |
IEEE Fukuoka Section, 九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
| 参加者 |
学生11名 教職員12名 学外107名 計130名 |
|
【プログラム】
| 13:00-13:05 |
開会挨拶 |
| 13:05-13:35 |
次世代電力網に向けた開閉機器の課題と今後の展望 |
|
|
 九州工業大学客員教授 石辺 信治 氏 九州工業大学客員教授 石辺 信治 氏 |
| 13:35-14:05 |
スマートグリッドの最近の動向と国際標準化 |
|
|
 九州大学教授 合田 忠弘 氏 九州大学教授 合田 忠弘 氏 |
| 14:05-14:50 |
次世代電力機器・システムの技術課題と展望 |
|
|
 株式会社東芝 高木 喜久雄 氏 株式会社東芝 高木 喜久雄 氏 |
|
(休憩) |
|
| 15:00-15:45 |
次世代電力網に向けた変圧器の課題と今後の展望 |
|
|
 株式会社日本AEパワーシステムズ 白坂 行康 氏 株式会社日本AEパワーシステムズ 白坂 行康 氏 |
| 15:45-16:30 |
スマートグリッド実証試験 |
|
|
 三菱電機株式会社 永野 亮淳 氏 三菱電機株式会社 永野 亮淳 氏 |
| 16:30-17:15 |
スマートグリッド/コミュニティに関する国の事業 |
|
|
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 諸住 哲 氏 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 諸住 哲 氏 |
| 17:15-17:20 |
閉会挨拶 |
| 17:30-19:00 |
講師との懇談会 |
 vol.5 vol.5
| 日 時 |
平成24年2月8日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
三菱電機株式会社
羽馬 洋之 氏 |
| 講演題目 |
「GISの進歩・動向と最新の絶縁技術」
|
| 参加者 |
学生27名 教職員5名 学外23名 計55名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
ガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear: GIS)は,誕生から40年以上が経過するが,これまで大きな電力需要の伸びを背景に高電圧/大容量・高信頼性・経済性という市場ニーズに応えて急速に進歩し,適用が拡大されてきた。近年では,経年GISの増加と地球環境問題がクローズアップされるようになり,初期コストのみならず運用コストや廃棄コストを含めたライフサイクルコストの低減,地球温暖化係数の高いSF6ガスの大気放出量の削減が求められるようになっている。
本講演では,GISの開発製品化の歴史と,それを支える基礎技術(絶縁技術,要素技術など)やブレイクスルー技術との関わりについて講演頂いた。また,最近の環境問題に対するGIS業界の取り組みや,講師がCIGREで主体的に取り組んでいる最新技術の調査状況,また諸外国のGIS関連技術の研究状況についてもご紹介頂いた。
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成24年1月18日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
九州工業大学 工学部 寄附講座(九州電力株式会社) 客員教授
石辺 信治 氏 |
| 講演題目 |
「避雷器の技術変遷と絶縁協調へのインパクト」
|
| 参加者 |
学生26名 教職員5名 学外28名 計59名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
欧米の多くの技術を応用・発展させてきた日本の高電圧技術史の中で,1970年代中頃に日本で発明された酸化亜鉛形避雷器は,日本から世界に発信してその後も先進性を維持してきた革新的技術の代表例としてあげられる。雷サージなどの過電圧から電力系統を守る避雷器は,酸化亜鉛形避雷器の登場により保護特性が画期的に良くなり,電力系統の信頼性・経済性に大きな変革をもたらした。優れた保護特性,構造の簡素さ,信頼性の高さに加え,その後の急速な性能進歩とコンパクト化もあいまって,酸化亜鉛形避雷器は,多様な形態で発変電所や送・配電線で適用・応用できるようになり,日本の電力系統の高い信頼性の礎の一つになっている。
本講演では,酸化亜鉛形避雷器の開発・技術進歩の経緯と,変電所や送・配電線での適用拡大の変遷及び絶縁協調へのインパクトについて講演していただいた。また,CIGRE/IECの避雷器関連活動状況と技術動向についても紹介していただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成23年11月9日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
三菱電機株式会社
亀井 光仁 氏 |
| 講演題目 |
「変電所機器診断技術の動向」
|
| 参加者 |
学生30名 教職員4名 学外38名 計72名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
電力設備の高経年化が進む中で,従来のように一定期間/機器動作回数ごとに点検を実施するTBM(時間基準保全: Time Based Maintenance)に対して,機器が現在どのような状態にあるかというセンシング情報を基に機器状態をトレンド監視し,必要な時期に必要な保守を行うCBM(状態監視保全: Condition Based Maintenance)管理が注目されている。機器状態のトレンドを数値評価することで,その評価結果を中長期の保守計画に反映し,巡視作業の合理化,点検の延期や高経年機器の更新時期延期などの具体的な経済効果が期待できる。
GIS(ガス絶縁開閉装置)のように密閉形機器では,機器内部の状態情報を如何にして得るかということが重要であり,その為には高性能センサが必要とされる。本講演では,GISのCBM管理を可能とする各種センサ及び監視システムの現状と技術動向について講演して頂いた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成23年7月28日(木) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
名古屋工業大学 工学部 教授
藤原 修 氏 |
| 講演題目 |
「静電気放電とEMC」
|
| 参加者 |
学生34名 教職員9名 学外11名 計54名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
静電気放電(ESD)は,EMCの概念が五十数年前に米国で確立される以前から電磁雑音源として既に認識されながら,今日なおEMCの解決すべき重要課題のひとつにあげられる。一方,電子機器の高性能化に伴いESDに対する機器イミュニティの重要性が叫ばれ,国際電気標準会議(IEC)では,ESDに対する機器イミュニティの試験法をIEC61000-4-2で規定してはいるものの,現場のESD障害については,イミュニティ試験をクリヤしても機器の誤動作事例が相変わらず報告される。現用試験法がESDを模擬していないことによるものと推察されるが,根源は,ESDの発生電磁界とその特性が未だもって十分に理解されていないことに起因する。この講演では,ESDの基本現象からESDによる発生電磁界を導出し,界の性質と特異特性を後に,講師のグループで行ってきたESDのFDTDシミュレーションとESDガン並びに帯電人体ESDに対する特性測定に関する研究成果について講演していただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成23年6月30日(木) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
財団法人 電力中央研究所 電力技術研究所 研究参事
岡本 達希 氏 |
| 講演題目 |
「電力設備のアセットマネジメント支援ツールの開発動向」
|
| 参加者 |
学生25名 教職員6名 学外24名 計55名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
近年の日本は経済の成熟期に入り,高度成長期に建設された膨大な社会インフラつまり電力や土木インフラにおける経年化が問題となりつつある。これに対し,設備のライフサイクルを考慮して保守や設備更新を考えるアセットマネジメントという技術の適用が始まっている。その基礎となる設備診断技術,寿命予測などの要素技術やアセットマネジメントの体系的考え方について電力分野を主体として講演していただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成22年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成22年度分)
 vol.7 vol.7
| 日 時 |
平成23年1月26日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
九州工業大学 工学部 寄附講座(九州電力株式会社)客員教授
戸田 弘明 氏 |
| 講演題目 |
「遮断器の技術と技術動向」
|
| 参加者 |
学生38名 教職員4名 学外13名 計55名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
日本の電力用ガス遮断器(Gas Circuit Breaker)の技術は,小形化,高電圧化,高信頼化を目指して展開してきており,現在世界で最高水準にある。そして,土地の狭い日本に適したガス絶縁開閉装置(Gas Insulated Switchgear)として地下変電所やUHV変電所にも適用されるようになった。一方,更なる高信頼性の確保や経済性の追求,そして環境への適合性なども叫ばれている。こういった状況下において,遮断器に課せられる責務とそれを支える技術をベースに今後遮断器の技術がどのように発展していくかその方向性と技術動向について講演いただいた。また,現在大学で行っている遮断器に関する基礎的な研究についても紹介していただいた。
 vol.6 vol.6
| 日 時 |
平成23年1月12日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
名古屋大学 工学研究科 教授
大久保 仁 氏 |
| 講演題目 |
「電力システムと電力機器の将来技術動向」
|
| 参加者 |
学生43名 教職員6名 学外28名 計77名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
近代社会における電気エネルギーの役割が大きく期待される中で,低炭素社会および環境適合社会に適合した次世代電力システム並びに電力機器の将来技術動向を議論いただいた。特に,基礎電気絶縁技術,Smart Gridや直流技術の適用,新しい材料技術などの技術展開,そして限流器などの新しい機能機器開発など,将来の超電導技術開発動向について講演いただいた。
 vol.5 vol.5
九州電力株式会社寄附講座 合同シンポジウム「電力関係の国際規格動向と戦略」
| 日 時 |
平成22年12月10日(金) 13:00 - 17:10 |
| 場 所 |
九州電力株式会社本店(電気ビル本館) B2F 7号会議室 |
| 参加者 |
学生10名 教職員10名 学外50名 計70名 |
| 主 催 |
九州大学 寄附講座(九州電力株式会社)「電気エネルギー環境工学講座」
九州工業大学工学部 寄附講座 (九州電力株式会社) 「電力系統制御工学講座」 |
| 共 催 |
IEEE Fukuoka Section, 九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
| 詳 細 |
 こちらをどうぞ こちらをどうぞ 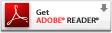 |
|
【プログラム】
| 13:00-13:10 |
開会挨拶 |
| 13:10-14:10 |
基調講演 |
|
IEC-SG3の動向 |
|
|
 九州大学客員教授 合田忠弘 氏 九州大学客員教授 合田忠弘 氏 |
|
電力関連技術の国際規格への取り組みについて |
|
|
 九州工業大学客員教授 戸田弘明 氏 九州工業大学客員教授 戸田弘明 氏 |
| 14:10-15:10 |
特別講演 |
|
スマートグリッドを巡る動向と我が国の取り組み |
|
|
 経済産業省基準認証政策課長 中西宏典 氏 経済産業省基準認証政策課長 中西宏典 氏 |
|
IEC/SMBの動向 |
|
|
 日本規格協会IEC/SMB日本代表委員 原田節雄 氏 日本規格協会IEC/SMB日本代表委員 原田節雄 氏 |
|
(休憩) |
|
| 15:20-17:05 |
パネルディスカッション (座長)九州大学教授 村田純一 氏 |
|
TC106(人体ばく露に関する電磁界の評価方法)の活動 |
|
|
 (財)電気安全環境研究所電磁界情報センター情報調査グループマネージャー 世森啓之 氏 (財)電気安全環境研究所電磁界情報センター情報調査グループマネージャー 世森啓之 氏 |
|
太陽光発電システムにおける国際標準化の現状と動向 |
|
|
 (独)産業技術総合研究所企画本部産業技術調査室総括主幹 津田 泉 氏 (独)産業技術総合研究所企画本部産業技術調査室総括主幹 津田 泉 氏 |
|
直流送電設備の変遷と規格化について |
|
|
 電源開発(株),IEC/TC115国内委員会委員長 境 武久 氏 電源開発(株),IEC/TC115国内委員会委員長 境 武久 氏 |
|
ディスカッション ─日本の技術をどのようにIEC規格に反映していくか─ |
| 17:05-17:10 |
閉会挨拶 |
| 17:20-18:50 |
講師との懇談会 |
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成22年11月11日(木) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
University of Stuttgart ドイツ
Prof. Stefan Tenbohlen |
| 講演題目 |
「Onsite Partial Discharge measurement of power transformers」
|
| 参加者 |
学生21名 教職員4名 学外16名 計41名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
電力用の油入変圧器の絶縁異常診断において部分放電計測技術は重要な役割を果たしている。本講演では,部分放電計測技術としてよく用いられているIEC60270による計測法の他に,音響検出法,UHF帯を測定対象とした部分放電放射電磁波検出による手法(UHF法)について,基礎的事項からフィールドへの適応例について紹介していただいた。UHF法は,広範囲かつ高感度な検出が可能であることから,最近,油入変圧器診断にも適用が活発に検討されている。また,UHF法と音響検出法を組み合わせた高精度な異常箇所の位置標定手法の適用例についても紹介していただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成22年10月20日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
同志社大学 教授
雨谷 昭弘 氏 |
| 講演題目 |
「電力系統における過渡現象解析の歴史と最近の動向」
|
| 参加者 |
学生40名 教職員6名 学外14名 計60名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
|
【概要】
電力系統における設備・機器の絶縁について検討するために過渡現象解析の研究が始められた。1910年代から1940年代までは実験的解析と理論解析がもっぱら用いられていた。その後,科学技術の変化,コンピュータ技術の発展,利用の一般化に伴い,数値シミュレーションに基づく過渡現象解析が実用に供されるようになってきた。また,最近,大型設備・機器と大量の人的・経済的資源を必要とする実現模レベルでの実験による過渡現象解析は影を潜め,数値シミュレーションが主流となっている。電力系統での過渡現象解析の歴史と変遷,および今後の動向について講演していただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成22年7月29日(木) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
財団法人 電力中央研究所 システム技術研究所
雪平 謙二 氏 |
| 講演題目 |
「電磁両立性と電力品質」
|
| 参加者 |
学生8名 教職員6名 学外29名 計43名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
|
【概要】
電磁両立性とはどういう意味か,日本の電力は品質がいいと言われているが,電力品質とは何を意味しているのか,電磁両立性とは何が違うのかを述べた後,電力品質を構成する主な要素(停電,適正電圧,周波数,三相不平衡,電圧変動とフリッカ,瞬時電圧低下,高調波電圧)について,評価方法と管理値,電力系統での状況,悪化原因,障害防止対策と対策上の問題点,再生可能エネルギー普及に伴う問題点などについてご講演していただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成22年5月7日(金) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
明治大学 理工学部 教授,社団法人 電気学会 会長
松瀬 貢規 氏 |
| 講演題目 |
「低炭素化社会に向けた電気電子工学への期待」
|
| 参加者 |
学生15名 教職員4名 学外44名 計63名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
|
【概要】
低炭素化社会に向けた重要な技術的手段の一つとして再生可能エネルギーの開発と普及がある。スマートグリッドなど賢い送電網として情報ネット,パワーエレクトロニクスを活用した電気エネルギーへの変換,電力系統への連係など電気電子技術が大きな役割を果たすことに期待が高まっている。講演ではエネルギー100年を概観し,再生可能エネルギーとその開発,新・省エネルギーを支える電気電子技術の概要についてご講演いただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成21年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成21年度分)
 vol.5 vol.5
| 日 時 |
平成22年1月20日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
名古屋大学 エコトピア科学研究所 教授
早川 直樹 氏 |
| 講演題目 |
「超電導技術の電力応用最前線」
|
| 参加者 |
学生43名 教職員4名 学外16名 計63名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
2011年は超電導の発見からちょうど100年に当たる。物理現象として発見された超電導は,運輸(リニア新幹線)や医療(MRI)の他,多くの技術分野への応用が期待されている。特に,電力・エネルギー分野では,超電導送電の実用化を目前にした実証試験が世界各国で進められている。本講演では,超電導の歴史・基礎,超電導電力機器の最新開発動向・技術課題を解説し,超電導が拓く次世代の環境調和・高機能型電力システムを概観していただいた。
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成21年12月16日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
財団法人 日本規格協会 IEC活動推進会議
原田 節雄 氏 |
| 講演題目 |
「企業戦略と国際標準化」
|
| 参加者 |
学生44名 教職員2名 学外16名 計62名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
近年,日本国内で国際標準化の重要性が叫ばれている。世界屈指の技術を誇る日本製の携帯電話機が海外で使えない。その国際市場占有率も8%(国内分だけ)に過ぎない。なぜ,このような事態に陥ったのか?
国際標準の成否は,技術の優劣ではなくて政治の巧拙で決まる。だが,日本の企業は建前の国際標準化を前に沈黙を続ける。欧米の企業は独り勝ちを目指す国際標準化の陰で暗躍を続ける。戦後からの日本経済の変化を貧困,成長,富裕の三相で捉え,今の日本と企業が抱える問題を国際標準化から解説し,また,日本が世界に先駆けて開発したJR東日本のスイカ導入時やUHV(100万V)送電の国際標準化を例に,人と組織の問題も解説していただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成21年11月18日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
株式会社 日本AEパワーシステムズ
白川 晋吾 氏 |
| 講演題目 |
「避雷器の技術展開でみる日本の電力技術 −雷,電力系統の絶縁協調と避雷器技術−」
|
| 参加者 |
学生40名 教職員3名 学外15名 計58名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
酸化亜鉛形避雷器は日本がオリジナリテイーを有し,主に雷サージ過電圧を抑制することから発変電所,配電線,送電線に広く適用されている。これらの状況を考え,日本の具体的貢献の内容が分かるように,電気学会技術報告書第1132号「避雷器の技術展開でみる日本の電力技術」を2008年9月に発行,2009年には英文の電気学会技術報告書「Lightning, Surge Arresters, and Insulation Co-ordination for Power Systems」を発信している。これらの主な内容について講演していただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成21年10月28日(水) 14:40 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
東京大学 生産技術研究所 教授
石井 勝 氏 |
| 講演題目 |
「数値過渡電磁界解析手法と雷サージ研究への応用」
|
| 参加者 |
学生39名 教職員5名 学外13名 計57名 |
| 共 催 |
九州パワーアカデミー
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
サージ解析手法の主流は,現在もEMTPに代表される回路解析手法である。しかし雷サージ,あるいは部分放電パルスが導体に沿って伝搬するときには,しばしば回路解析が前提とするTEMモードの電磁界とかけ離れた電磁界分布になることがある。送電鉄塔に落雷した際の初期の電磁界分布が典型例である。近年,マックスウェルの方程式を数値的に解く手法のサージ解析への適用が実用化され,雷サージ研究に威力を発揮していること等を講演していただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成21年8月5日(水) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
株式会社 東芝
西脇 進 氏 |
| 講演題目 |
「ガス絶縁開閉機器の適用,運用と設計に考慮されるべき高電圧開閉現象」
|
| 参加者 |
学生13名 教職員7名 学外42名 計62名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
|
【概要】
変電所における開閉機器は,事故の除去や系統の運用のために開閉操作され,この時発生する過渡現象に耐え,また,系統に害を与えてはならない。電力系統の発展に伴って新たな機能も要求される。ガス絶縁開閉機器について,その適用,運用と設計に考慮されるべき高電圧開閉現象について,基本を確認し,さらに最近の経験を数多く報告を講演いただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成20年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成20年度分)
 vol.8 vol.8
| 日 時 |
平成21年3月30日(月) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
KEMA High-Power Laboratory (オランダ電気機器規格協会)
Prof. Smeets, Rene Peter Paul |
| 講演題目 |
「配電系統電圧における遮断技術」
|
| 参加者 |
学生12名 教職員6名 学外25名 計43名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部
|
|
【概要】
導入部分では,配電系統における短絡事故の様相のいくつかをビデオにて紹介いただいた。次に,配電系統での遮断器の機能について説明し,遮断の基本的な概念から,遮断の際の問題点を解説し,アークの起源と役割および回復電圧について議論した。その後,低電圧遮断の原理と本質的な故障電流の制限について,モールドした比較的小さな遮断器を例に説明いただいた。次に,遮断器開発の変遷を紹介した後に,配電系統における遮断現象・遮断器の最新技術,すなわち,SF6ガス遮断器および真空遮断器について解説し,これらの遮断器の動作原理と特にスイッチング真空アークの物理について解説いただいた。
また,真空遮断器内での適切なアーク制御に対する有効な技術的解決法と共に,真空中における短絡電流遮断の問題点を述べ,非持続的な破壊的放電,真空の漏れ,それらの影響,多重再点孤,関連する他の機器へのストレスなどの種々の電気的局面についても議論した。最後に,真空遮断器の将来展望とその限界についても,講演者の視点を紹介いただいた。
 vol.7 vol.7
| 日 時 |
平成21年2月27日(金) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 総合研究棟 2F S-2A講義 |
| 講演者 |
西安交通大学 電気絶縁電力機器国家重点研究所 教授
鐘 力生 氏 |
| 講演題目 |
「中国における電力技術の教育と研究」
|
| 参加者 |
学生7名 教職員7名 学外9名 計23名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
西安交通大学における電力工学の教育の発展および現状,中国国家重点研究所の位置付け,電気絶縁電気機器国家重点研究所でおこなっている電力機器に必要とされる絶縁材料と電気絶縁手法に関する最近の研究内容の紹介をいただいた。さらに中国におけるUHV送電システムの必要性について討論し,このシステムで電力機器メーカに及ぼす機会と挑戦について講演いただいた。
 vol.6 vol.6
| 日 時 |
平成21年1月13日(火) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
東日本旅客鉄道株式会社
林屋 均 氏 |
| 講演題目 |
「電気鉄道の電力供給システムと最近のパワーエレクトロニクス応用」
|
| 参加者 |
学生26名 教職員6名 学外20名 計52名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
鉄道はエネルギー効率が高く,環境負荷の小さい移動手段である。例えば,ひとりを1km運ぶときの鉄道のCO2排出量は,乗用車の約1/9,航空機の約1/6と,鉄道の環境優位性の高さが伺える。
その列車運行に欠かせない電力技術。本講演では,まず電気鉄道への電力供給システム(き電システム)の概要を説明し,通常の電力系統との違いを意識しながらその電力設備の成り立ちを解説いただいた。その上で,電気鉄道の安定輸送を支える最新のパワーエレクトロニクス応用事例を幾つか紹介いただいた。JR東日本の東北新幹線に導入されている電力補償装置(RPC)やつくばエクスプレスで実用化された直流変電所用PWMコンバータ,JR東海が採用している静止形周波数変換装置など,電気鉄道ならではのパワーエレクトロニクス応用事例のほか,鉄道固有性の高い直流遮断技術や新幹線の切替開閉器システムにも適用されつつある新しいパワーエレクトロニクス技術についても紹介いただいた。
 vol.5 vol.5
| 日 時 |
平成20年12月2日(火) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
(財)電力中央研究所 首席研究員
横山 茂 氏 |
| 講演題目 |
「高度情報社会の安全と自然エネルギーの普及に貢献する雷害対策技術」
|
| 参加者 |
学生22名 教職員5名 学外60名 計87名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
現在でも停電は年間数千件発生しておりその3分の1は雷によるものである。停電には至らないものの,瞬時の電圧低下も,高度情報社会では与える影響が重大になっているが,そのほとんどは雷に起因している。また,一般家庭でも,パソコンの普及や家電製品にマイコンが内蔵されるようになり,雷サージに脆弱になっている。
高度情報社会では,電気に対する信頼性の要求はますます強くなる一方,雷害対策はできるだけ小さい費用で効率よく構築することが求められている。本講演では,送電線や配電線など電力設備の雷害対策の現状と,家電製品の雷害状況と対策の方向性について,研究の成果を基に解説いただいた。また,近年大きな問題になっている風力発電設備の雷害についても,実験の結果を踏まえて,問題点を明らかにした。さらに,長い研究の継続にもかかわらず,雷には,いまだに未解明の現象が数多くあることを,近年の観測結果を交えながら説明いただいた。
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成20年10月21日(火) 12:50 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
(株)東芝 ・ 昭和電線電纜(株)(現 昭和電線ホールディングス(株)) OB
長谷 良秀 氏 |
| 講演題目 |
「技術の心,技術者のプライド・スピリツとステータス −メーカ技術者の体験から−」
|
| 参加者 |
学生23名 教職員5名 学外20名 計48名 |
| 共 催 |
電気学会九州支部
|
| 協 賛 |
電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
講師は長年メーカに勤務して電気・電力関係の仕事に携わってきた。その実体験を通じて体得した技術の心,技術者が等しく抱くべきプライド(Pride)とスピリツ(Spirit),そして勝ち取るべきステータス(Status)について若い技術者に語りかけました。未来を背負う学生諸君はいかなる姿勢で技術と対峙すべきか。技術者を志向する若い学生諸君がぜひ自分のものとして獲得すべき物の見方,技術への取り組み方,専門性に対する考え方等について自らの考えを披露いただきました。さらに最近の技術進歩の一端を紹介しつつ,電気技術は若い人々が life work として打ち込む価値のある仕事であることを解説いただきました。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成20年10月1日(水) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学 工学部総合教育棟 C-1B講義室 |
| 講演者 |
シェフィールド大学 英国
Prof. Shankar Narayanan Ekkanath Madathil |
| 講演題目 |
「Power Microelectronics - my perspective」
|
| 参加者 |
学生34名 教職員7名 学外5名 計46名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
次世代パワーエレクトロニクス・電力用半導体の分野で先進的な研究を進めている Shanker Madathil 氏は,この分野の国際的キーマンの一人であり,現在インド・日本・欧州の電力・パワエレ関係の研究機関や企業と関係をもっておられます。今後存在感の大きくなるインドなどとの国際連携などを視野に入れ,パワーエレクトロニクス及びパワー半導体の分野での最新技術開発や研究の方向まで含め講演いただきました。今回は「パワー・マイクロエレクトロニクス」と題して,特に最先端半導体技術とパワー制御やエネルギーマネジメント技術の融合,及びそこで用いられるキーデバイスであるパワー半導体についてご講演いただきました。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成20年5月26日(月) 17:50 - 19:20 |
| 場 所 |
九州工業大学 工学部総合教育棟 C-1C講義室 (共南11) |
| 講演者 |
キングモンクット工科大学(KMITL) タイ
Ngamroo Issarachai 准教授 |
| 講演題目 |
「東南アジア諸国における電気エネルギー事情」
|
| 参加者 |
学生47名 教職員5名 学外5名 計57名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
Ngamroo先生は主に電力系統の解析・制御に関する研究をされています。タイの電力公社(EGAT)と電力系統制御の研究の実施やタイエネルギー省の委託でホテルやビルの省エネルギー化の仕事など幅広い活動をされています。今回,共同研究のために来日されている機会を利用して,東南アジアのエネルギー,特に電気エネルギーに着目した現状や将来見通しの話,それからタイの電力系統の動特性やマレーシアとの直流連系を利用した制御などを紹介いただき,先生の専門分野である,位相計測器(PMU)を用いてタイの電力系統の動揺を計測した結果や,最近の電力系統安定化制御に関する研究成果を紹介いただきました。Ngamroo先生は大阪大学で博士前期課程と後期課程を修了し,工学博士を取得された後にタイの大学に戻って居られ,英語のスライドを用いて,可能な範囲の日本語でのわかりやすい解説を頂きました。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成20年4月30日(水) 10:30 - 12:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
マサチューセッツ工科大学(MIT)
Dr. C. M. Cooke |
| 講演題目 |
「絶縁不良に関与する基礎現象」
|
| 参加者 |
学生35名 教職員4名 学外8名 計47名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
Cooke先生は,米国MITにて固体絶縁物の帯電現象や高電圧工学の研究に取り組んで来られた,世界で著名な研究者です。今回,九州へお越しいただいた機会を利用して,掲題の講演をお願いしました。絶縁不良はまったく異なるミクロな現象の連続で発生するという性質を持っているので,統計的な特性を有しています。統計的な現象であることから,確率で発生する絶縁不良が,絶縁物の寿命を決めるということに着目して,関連する基礎現象を解説していただきました。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成19年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成19年度分)
 vol.12 vol.12
| 日 時 |
平成19年12月19日(水) 10:30 - 12:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 総合研究棟 2F S-2B (大学院ゼミ室) |
| 講演者 |
フランス ポールサバティエ大学CNRSエネルギー変換誘電材料研究グループ研究室長
Prof. Thierry Lebey |
| 講演題目 |
Dielectric Spectroscopy for the Characterization of Insulating and Dielectric Materials used in Power Electronics Applications
「パワ−エレクトロニクス応用に使用される誘電絶縁材料の物性解明のための誘電的スペクトロスコピー」
|
|
【概要】
誘電的スペクトロスコピー(DS)は誘電絶縁材料分野では実用的で一般に使用されるツールである。本講演では,DSの2つの例を紹介した。最初は,高電圧高温半導体デバイスのパッシベーション用の材料であり,ポリイミドPIの電気伝導を200〜400℃で測定した。この結果から,低周波分散(LFD)アプローチを用いて,ε′, ε″と導電率を解析した。ポリイミドの高温静的直流伝導率は,直流金属・絶縁体・金属のバルク・電極界面での薄い空間電荷キャパシタ層の形成による電極分極の重畳として現れ,そのため直流導電率の評価が難しい。一方,動的交流伝導率の周波数特性から,PIの直流伝導率の近似解が得られた。2つめの例は,DSを巨大誘電率材料の物性評価に用いた。ここでは,機械特性とインピーダンスデータを用いて,この巨大誘電率が生ずる原理について検討している。
 vol.11 vol.11
| 日 時 |
平成19年12月18日(火) 15:00 - 16:15 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
フランス ポールサバティエ大学CNRSエネルギー変換誘電材料研究グループ研究室長
Prof. Thierry Lebey |
| 講演題目 |
Partial Discharges in Power Electronics Applications
「パワ−エレクトロニクス応用での部分放電」
|
| 参加者 |
学生13名 教職員4名 学外25名 計42名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
低電圧非同期モータに対して高速スイッチングデバイスによる可変速駆動を使用することはその信頼性にとり最も重要な点である。その際に,絶縁材料の早期の欠陥はしばしば巻線での部分放電(PD)に起因する。一方,PD現象はパワーモジュールレベルでも存在する。この講演では,低圧回転機のオフライン試験の開発から高電圧(6.5kVまで)IGBTパワーモジュールの試験まで紹介いただいた。さらに,このパワーモジュールでのPD現象の新しい分野の話題について紹介いただいた。すなわち,準電気飛行機(More Electric Aircraft)あるいは電気飛行機(All Electric Aircraft)などの新しい航空機用電力の需要が増大し,ここで使用される電気部品・デバイスが圧力・湿度の極限環境状態で使用され,電圧レベルも増大している。すなわち,これらのデバイスが圧力がかかる領域あるいは圧力がかからない領域に置かれる。それゆえ,環境条件が-60℃〜+250℃,圧力が1気圧〜100mbar,湿度が0〜100%となる。これらのすべてのパラメータが装置の部分放電開始電圧(PDIV)に影響を与える。この観点から,パッシェンカーブをこれらの環境条件で再プロットする必要がある。この特殊環境でのPDIVを測定するための実験装置を構築した。この研究の最終ゴールは,最も悪い条件でのPD開始を決定することであり,電気飛行機の運航中での信頼性向上を目指して部分放電開始を避ける技術について講演いただいた。
 vol.10 vol.10
| 日 時 |
平成19年12月18日(火) 12:50 - 14:20 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
住友電気工業株式会社 材料技術研究開発本部 支配人
佐藤 謙一 氏 |
| 講演題目 |
「超電導技術 新しい電気と磁気の応用」
|
| 参加者 |
学生23名 教職員5名 学外6名 計34名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
佐藤氏は,超電導線材からケーブル等関連機器までの開発に携わってこられ,超電導研究の専門家である。また,国際電気規格IECでは,超電導関連の技術委員会TC90の国際幹事を務められ,超電導の規格化を進めている。これら佐藤氏の活動内容を講演していただいた。
 vol.9 vol.9
| 日 時 |
平成19年12月17日(月) 12:50 - 14:20 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 総合研究棟 2F S-2A |
| 講演者 |
フランス ポールサバティエ大学CNRSエネルギー変換誘電材料研究グループ研究室長
Prof. Thierry Lebey |
| 講演題目 |
Power Electronics Hybrid Integration
「パワ−エレクトロニクスでのハイブリッド集積技術」
|
| 参加者 |
学生23名 教職員2名 学外6名 計31名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
集積化はパワ−エレクトロニクス(PE)応用においてもどんどん進んでいる。この集積化により構成要素の密度が上昇するとともに(熱的・電磁的の両面での)ストレスの上昇に至る。この講演では,パワ−エレクトロニクスデバイス集積化に関してポールサバティエ大学CNRS エネルギー変換誘電材料研究グループにて開発された研究成果を通して誘電および絶縁材料の役割に焦点を当ててお話しいただいた。最初の部分では,パッシブとアクティブな集積化の両面に対して必要な理由について,実際の応用(鉄道,自動車および航空機)でのいくつかの例を紹介いただいた。さらに,パワーハイブリッド集積化分野でなされた他の結果についても議論した。高電圧高温半導体デバイス(SiCなど)のパッシベーション用の可能な材料研究の成果報告から始まり,封入用材料,基盤材料,結線技術,ストレス緩和材料,高誘電率・巨大誘電率材料の研究を通してシステムレベルでの誘電試験について紹介された。最後に,パワ−エレクトロニクスの将来動向および鉄道への応用における開発中の研究(高周波,高電圧構造)について紹介いただき議論した。
 vol.8 vol.8
九州電力株式会社寄附講座 合同講演会(第2回) 「技術基準の国際化への対応について」
| 日 時 |
平成19年12月3日(月) 13:30 - 17:00 |
| 場 所 |
九州電力株式会社 本店 (電気ビル本館) 地下2階 7号会議室 |
| 主 催 |
九州大学 電気エネルギー環境工学講座, 九州工業大学 電力系統制御工学講座 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Kyushu Chapter
|
| 詳 細 |
 こちらをどうぞ こちらをどうぞ 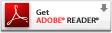 |
|
【プログラム】
| 13:30 |
開会 |
| 13:30 - 13:40 |
開会挨拶 |
| 13:40 - 14:40 |
講演1: 「新技術導入を考える」で学ぶ −1/温故知新− |
|
|
 電気学会会長 電力中央研究所技術顧問 東大名誉教授 仁田 旦三 氏 電気学会会長 電力中央研究所技術顧問 東大名誉教授 仁田 旦三 氏 |
| 14:40 - 14:50 |
(休憩) |
|
| 14:50 - 15:50 |
講演2: 「国際標準化への取り組みの重要性」 |
|
|
 経済産業省産業技術環境局 経済産業省産業技術環境局 |
|
|
情報電子標準化推進室長(兼)管理システム推進室長 和泉 章 氏 |
| 15:50 - 16:00 |
(休憩) |
|
| 16:00 - 16:15 |
講演3: 「モンゴルでの標準化活動についての報告」 |
|
|
 九州大学教授 合田 忠弘 九州大学教授 合田 忠弘 |
| 16:15 - 16:30 |
講演4: 「UHV国際標準化活動の経過報告」 |
|
|
 九州工業大学教授 池田 久利 九州工業大学教授 池田 久利 |
| 16:30 - 17:00 |
パネルディスカッション |
| 17:00 |
閉会 |
| 17:10 - 18:30 |
懇親会 (電気ビル本館B4F ウオクニ) |
 vol.7 vol.7
| 日 時 |
平成19年11月20日(火) 12:50 - 14:20 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 総合研究棟 2F S-2A |
| 講演者 |
東京大学
石井 勝 氏 |
| 講演題目 |
「雷の基礎現象と送電線の保護」
|
| 参加者 |
学生22名 教職員3名 学外29名 計54名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEI Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
石井先生は30年以上の長期間に渡って雷現象の研究に従事してこられた日本の権威で,世界の雷に関する学会で要職につかれています。電力系統事故の40%は雷撃によるものといわれていますが,近年気候変動の影響もあり,雷による被害を耳にする機会が多くなっております。雷撃から電力機器を守ることは従来にもまして重要なテーマです。雷現象特に冬季雷を中心に,電力系統の事故に関与する雷の基本的な特性を解説していただくとともに,電力系統を雷から守る対策についてご講演いただいた。
 vol.6 vol.6
| 日 時 |
平成19年11月15日(木) 15:00 - 17:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
株式会社東芝 電力産業システム技術開発センター
西脇 進 氏, 野呂 康宏 氏 |
| 講演題目 |
「長距離交流ケーブル送電系統の課題と対策:五島連系について」
|
| 参加者 |
学生15名 教職員6名 学外21名 計42名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
九州と五島を結ぶ連系は,過去に例のない66kV 54kmの長距離交流ケーブル連系である。主としてケーブルの静電容量が大きいことで発生する多くの課題が解決された。新しい過渡現象が想定されて対策が実施された。また,電圧変動抑制のためにSVC(静止型無効電力調整装置)が導入された。これら課題解決に当たって,解析を担当した西脇氏と野呂氏に講演していただいた。
 vol.5 vol.5
| 日 時 |
平成19年10月30日(火) 15:00 - 17:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4F AVホール |
| 講演者 |
ジーメンス社 送配電部門
Dr. Herman Koch 氏 |
| 講演題目 |
「SF6ガス絶縁機器」
|
| 参加者 |
学生11名 教職員5名 学外12名 計28名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
|
|
【概要】
Koch氏は,IEC(国際電気技術協会)の開閉装置部会,SC17Cの幹事を務め,この分野で著名な専門家である。ドイツSiemens社ではガス絶縁線路の開発に取り組んできた。また,米国IEEE開閉機器部会の副部会長をつとめている。この部会では,ガス絶縁送電線,ガス絶縁開閉装置,SF6ガスに関する技術報告を取りまとめている。この技術報告には世界の開閉装置メーカの技術内容が含まれている。この教材を中心に,世界の開閉装置技術の現状を報告していただいた。
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成19年10月16日(火) 12:50 - 14:20 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 総合研究棟 2F S-2A |
| 講演者 |
東京電力株式会社
岡本 浩 氏 |
| 講演題目 |
「1100kV UHV送電技術」
|
| 参加者 |
学生23名 教職員5名 学外14名 計42名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
1100kV交流のUHV送電は既に30年以上に渡って日本で研究されてきた。中国ではこの日本の技術を用いたパイロットプラントが建設され,2008年には運用される予定である。このUHV送電には,色々な新しい技術や極限的な技術が盛り込まれている。岡本氏は東京電力株式会社殿でUHV送電とその国際規格化に取り組まれている。最新の事業環境を含めて,技術の全体像を講義していただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成19年8月23日(木) 15:00 - 17:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
コネチカット大学 電気物理学部教授 絶縁材料研究所所長
トロント大学 電気コンピュータ学部教授
Prof. Steven Boggs |
| 講演題目 |
「避雷器の非線形熱電気解析」
|
| 参加者 |
学生7名 教職員7名 学外7名 計21名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
【概要】
高電圧工学では,新しい材料や環境による汚損などが開発に大きな影響を及ぼすようになってきており,電磁気学や回路理論では解明できない,非線形現象の研究が大きな課題となっている。Boggs教授は,コネチカット大学の絶縁材料研究所所長として,長い間非線形解析手法の開発に取り組んできている。講演では,高電圧工学における非線形解析の適用について,事例で紹介していただき,非線形解析の有用性をご説明いただいた。また,非直線性が顕著な避雷器への適用についてご紹介いただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成19年7月25日(水) 10:00 - 11:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
フランス電力 クラマー研究所
Mr. Robert Jeanjean |
| 講演題目 |
「電力設備更新の電力会社基本方針」
|
| 参加者 |
学生15名 教職員6名 学外27名 計48名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
|
|
|
|
|
 Jeanjean氏 Jeanjean氏 |
 講演の様子 講演の様子 |
 会場の様子1 会場の様子1 |
 会場の様子2 会場の様子2 |
|
【概要】
電力用設備は,特に欧米や日本の先進国において,使用年数が30年を越えるものが多くなってきている。老朽化に伴う設備更新を合理的に行うことは電力会社の経営に大きな問題となっている。このため,フランス電力では「設備更新の基本方針」を定めている。講師のJeanjean氏は同社のパリ郊外にあるクラマー研究所で電力用遮断器を中心に,電力機器の電気的機械的寿命試験法の開発に取り組み,国際規格IECにその試験法を反映してきた。この分野では世界的にもトップレベルの専門家である。今回の講演では遮断器などの電力機器の寿命を確保する機械的電気的試験法の重要性と,試験を考慮した同社の「設備更新の基本方針」についてご講演いただいた。また,最近の同社の設備更新の実例をご紹介いただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成19年5月18日(金) 15:00 - 17:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
三菱電機株式会社 系統変電システム製作所
土江 基夫 氏 |
| 講演題目 |
「変圧器診断における油の分析法の最新技術動向」
|
| 参加者 |
学生23名 教職員4名 学外39名 計66名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE PES Fukuoka Chapter
|
|
|
|
【概要】
電力用変圧器は,国内外とも,使用年数が30年を越えるものが多くなってきている。老朽化に伴う設備更新を合理的に行うために,変圧器の状態診断技術が注目されており,変圧器油の分析は変圧器の状態診断に欠かせない技術となっている。講師の土江氏は三菱電機の変圧器工場で30年以上に渡って,油分析に関する研究を行ってきた。この分野では世界的にもトップレベルの専門家であり,変圧器診断における油の分析法の最新技術動向として,絶縁油や絶縁材料から発生するフルフラール等の微量な物質の分析法について講演いただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成18年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成18年度分)
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成19年1月26日(金) 15:00 - 17:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
九州大学名誉教授,九州電力株式会社総合研究所顧問
原 雅則 氏 |
| 講演題目 |
「超電導とバイオの分野における高電界現象」
|
| 参加者 |
学生18名 教職員4名 学外17名 計39名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,IEEE DEIS Fukuoka Chapter
|
|
|
|
【概要】
超電導体のクエンチ現象を考慮した電力用超電導機器の絶縁設計技術の確立,ならびに電力輸送設備近傍における電磁環境と電界の生体など周囲環境に及ぼす影響に関する研究を,特に「問題の発見」,「問題の解決に向けた展開」の面から講演いただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成18年12月19日(火) 15:00 - 17:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所電機システム技術部
兼田 吉治 氏 |
| 講演題目 |
「回転機のPD計測・診断の最新技術開発動向」
|
| 参加者 |
学生17名 教職員5名 学外21名 計43名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEIS Fukuoka Chapter
|
|
|
|
【概要】
回転機のPD計測と診断技術を概観し,近年ニーズが高い設備の信頼度を維持しながら保全コストの低減を実現できるオンラインPD計測と絶縁診断技術の開発動向についてご講演いただいた。また,三菱電機での開発実例をご紹介いただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成18年12月12日(火) 15:00 - 17:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
株式会社ビスキャス 技術本部研究開発部部長
渡辺 和夫 氏 |
| 講演題目 |
「電力ケーブルの技術開発動向と絶縁診断技術」
|
| 参加者 |
学生19名 教職員5名 学外16名 計40名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部,電気設備学会九州支部,IEEE DEIS Fukuoka Chapter
|
|
|
|
【概要】
電力輸送を担う電力ケーブルの500kV級超高電圧化に向けてのこれまでの技術開発動向と,現在益々ニーズの高まっている劣化診断や寿命診断に繋がる絶縁診断技術の開発動向を概観し,将来の方向性についてご講演いただいた。 また,理論上にも実用上にも大変有用な関数である「楕円関数」の電力ケーブル問題への二,三の応用例をご紹介いただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成18年6月26日(月) 14:00 - 16:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
琉球大学 工学部電気電子工学科
金子 英治 教授 |
| 講演題目 |
「沖縄の電力事情と高電圧・電力技術者の取り組み」
|
| 参加者 |
学生23名 教職員5名 学外21名 計49名 |
| 協 賛 |
電気学会九州支部
|
|
|
|
【概要】
沖縄は亜熱帯の離島により構成され,生活の基盤である電力については,他の電力会社とは連携できず小さく閉じられた電力系統の中で,供給,需要のバランスを保たねばならない。特に,沖縄の電力需要は,夏季においては,昼夜間の格差が極めて大きく,その反面,冬期にはほとんど昼夜間の格差は無いため,電力設備の経済的運用に関しては大きな課題がある。現在,フライホイールによる負荷均衡,海水揚水発電の実運用がなされているが,さらに風力,太陽光,大容量電池の採用など,他に先駆けた新しい電源技術の積極的導入,使用を行おうとする技術先取りの検討が行われている。本講演では,このような実例を解説しながら,沖縄における今後の電力技術,特に高電圧,大電力技術に関連する技術への取り組みをご紹介いただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成17年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成17年度分)
 vol.6 vol.6
| 日 時 |
平成17年10月7日(金) 13:00 - 15:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 総合研究棟2階 大学院ゼミ室 |
| 講演者 |
首都大学東京大学院 工学研究科 システム基礎工学専攻
武藤 信義 教授 |
| 講演題目 |
「電力変換器・駆動システムの電磁ノイズ抑制技術とその電気自動車への応用」
|
| 参加者 |
学生17名 教職員5名 学外24名 計46名 |
|
|
|
【概要】
インバータに代表されるパワーエレクトロニクス装置は環境調和型のエネルギー変換器として一般産業用から家電・交通・電力まで幅広く使用されている。近年のパワー半導体の高出力化・スイッチング速度の高速化に伴い,電磁ノイズの抑制が重要性を増している。本講演ではその原因・対策について解説いただくとともに,特に急速に拡大しているハイブリッドカーのような電気自動車(EV)における応用事例についてご紹介いただいた。
 vol.5 vol.5
| 日 時 |
平成17年10月4日(火) 14:00 - 16:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
東京大学名誉教授
工学博士 河村 達雄 氏 |
| 講演題目 |
「電力技術と設備診断」
|
| 協 賛 |
電気学会九州支部
|
| 参加者 |
学生14名 教職員5名 学外16名 計35名 |
|
|
|
|
|
|
 河村名誉教授 河村名誉教授 |
 講演の様子1 講演の様子1 |
 講演の様子2 講演の様子2 |
 質疑の様子 質疑の様子 |
|
【概要】
電力技術は,経済の高度成長の時代から安定成長に移行するそれぞれの時代の社会ニーズに対応して展開されている。これらの変遷と,その時々での技術開発の動向が紹介され,あわせて,これからの社会ニーズに適応するための技術展開として,設備診断をふくむ電力技術の課題について講演いただいた。海外では盛んに議論が進められているライフサイクルコスト,アセット・マネジメントの今後の展開が注目されるとのことである。
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成17年8月6日(土) 10:00 - 12:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気別館2階 ゼミ室 |
| 講演者 |
株式会社東芝 浜川崎工場変圧器部,前寄附講座客員教授
工学博士 池田 正巳 氏 |
| 講演題目 |
「電力変電設備の発展」
|
| 参加者 |
学生6名 教職員5名 計11名 |
|
|
|
【概要】
変圧器,遮断器(GIS),避雷器,変流器,直流送電といった電気エネルギー輸送には不可欠な電力変電設備の最新技術について,写真を多用して平易に講演いただいた。とくに変圧器の製造技術,ガス絶縁変圧器(GIT)のCAE技術については動画を用いて紹介していただき,非常に興味深い内容であった。池田氏はガス絶縁変圧器開発のプロジェクトリーダを務められ,開発過程で生じる諸問題の克服にご尽力されたとのことである。聴講者は少ないながらも活発な質疑が交わされ,非常に有意義であった。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成17年6月7日(火) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
フランス ポールサバティエ大学
Thierry Lebey 博士 |
| 講演題目 |
「パワーエレクトロニクスのモジュール統合の最新動向: 誘電・絶縁材料の役割」
"New trends in Power Electronics integration: the key role of insulating
and dielectric materials" |
| 参加者 |
学生30名 教職員4名 学外15名 計49名 |
|
|
|
|
|
|
 Lebey博士 Lebey博士 |
 講演の様子1 講演の様子1 |
 講演の様子2 講演の様子2 |
 質疑の様子 質疑の様子 |
|
【概要】
インバータ電源は通常,パワー素子と制御回路を一体化したインテリジェントパワーモジュール(IPM)として提供されている。IPMにおいては複数の素子からの発熱による温度分布,電界分布,大電流による電磁干渉などを最適に抑制するため,冷却方式・高熱伝導構造・電界緩和構造,シールドなどを総合的に最適化する技術(integration;統合)が極めて重要である。パワー素子や配線用のプリント基板,表面および全体を封止する誘電・絶縁材料の選択・最適組合せがシミュレーションを駆使して研究されている。EUでは国境を越えて産学連携による共同研究が進められている。この最新動向について,実験データを交えつつ図や写真を多用して講演いただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成17年6月2日(木) 14:00 - 15:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気別館2階 ゼミ室 |
| 講演者 |
米国 MIT(マサチューセッツ工科大学)
Chathan M. Cooke 教授 |
| 講演題目 |
「変圧器に関する最新オンライン部分放電計測」 |
| 参加者 |
学生25名 教職員4名 計29名 |
|
|
|
|
|
|
 Cooke教授 Cooke教授 |
 講演の様子1 講演の様子1 |
 講演の様子2 講演の様子2 |
 講演者を囲んで 講演者を囲んで |
|
【概要】
電力用変圧器の最新のオンライン部分放電検出法の原理とその結果について,平易な英語説明をしていただいた。米国における英語の授業を彷彿とさせる雰囲気で学生からも活発な質疑があった。また,関連の研究室見学においても活発に議論した。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成17年5月24日(火) 14:30 - 16:00 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
首都大学東京大学院 工学研究科 電気工学専攻
横山 隆一 教授 |
| 講演題目 |
「競争環境下での分散型電源の役割と次世代エネルギーシステム」 |
| 参加者 |
学生42名 教職員5名 学外27名 計74名 |
|
|
|
【概要】
電力自由化は世界的な流れであり,我が国においても2005年4月より受電電力50kW以上の需要家まで自由化対象が拡大されている。さらに,分散型電源の導入も急速に進んでおり,電力システムを取り巻く環境はますます複雑となっている。近年著しい変化が見られるエネルギー流通システムの世界動向について,以下の多岐にわたる項目について講演いただいた。
・ 諸外国における電力自由化と市場形成の動向
・ 競争環境下での電力市場構造と取引形態
・ 電力自由化の下での大規模停電事故の様相と背景
・ 供給信頼度維持のための送電混雑管理と解消方法
・ 競争環境下の系統運用における分散型電源の役割
・ 分散型電源有効活用のための次世代エネルギー流通システム
・ 次世代エネルギー流通システムの実証プロジェクト
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成16年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成16年度分)
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成16年10月19日(火) 9:40 - 10:40 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気別館2階 ゼミ室 |
| 講演者 |
英国 レスター大学
客員教授 Jeremy C. G. Wheeler 氏
カナダ アイリス社 前社長・技術部長
工学博士 Greg Stone 氏 |
| 講演題目 |
「高電圧機器絶縁の製造技術」
「技術者の組織上の立場と真の役割」 |
| 参加者 |
学生18名 教職員4名 学外3名 計25名 |
|
|
|
|
|
|
 Wheeler客員教授 Wheeler客員教授 |
 Stone博士 Stone博士 |
 講演の様子1 講演の様子1 |
 講演の様子2 講演の様子2 |
|
【概要】
高電圧機器では部分放電の発生が運転寿命に影響するため,製造時点で微小な欠陥を極力除去する必要がある。Wheeler氏は英国GEC社(現アルストーム)スタッフォード工場において固体絶縁体内の微小欠陥除去・評価技術を担当した。固体絶縁設計製造のポイントと金型不要の高圧ポリマーブッシングや各種の製造技術について写真を多用して平易に講演いただいた。
Stone氏はカナダ最大の電力会社オンタリオハイドロにおいて,発電機オンライン部分放電検出装置を開発するとともにIEEEの技術委員会で広く活動してきた。その後,1992年ベンチャー企業「アイリス」を設立し、世界中で絶縁診断技術の普及とビジネスを手がけている。大組織とベンチャーの両体験を踏まえ,若手技術者に対し組織上の立場と真の役割について率直な意見を講演いただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成16年7月16日 13:30 - 16:30 |
| 場 所 |
九州工業大学 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
東京大学 生産技術研究所
石井 勝 教授 |
| 講演題目 |
「電気設備における電気的サージ現象とその予測手法」 |
| 参加者 |
学生26名 教職員5名 学外11名 計42名 |
|
|
【概要】
電気的サージ現象とは,送電線や配電線などの線路に生じる過渡現象のうち,線路やそれにつながる装置,回路などの絶縁を脅かす種類の過電圧である。
この現象解明には観測のみならずマックスウェル方程式ならびに波動方程式に基づく理論的取り扱いが重要となる。
実例として送電線への雷撃についてサージ電圧ならびにサージ電流の最近の観測事例を取り上げ,雷サージを線路上の進行波としての取り扱いについて3次元電磁界解析を中心に最近の研究動向を紹介して頂いた。
また,高電圧測定で使用される分圧器の応答特性について,特に重要なシールド電極の影響について電磁気学との関係や電気回路としての取り扱いとの関係について最新の研究動向を含め幅広く講演いただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成16年6月22日 13:00 - 16:10 |
| 場 所 |
九州工業大学 附属図書館 本館4階 AVホール |
| 講演者 |
大阪府建築都市部公共建築室 設備課(設備計画G)
課長補佐 田邊 陽一 氏 |
| 講演題目 |
「ESCO事業の活用によるビルの省エネルギー化とエネルギーコスト削減
−大阪府の取り組みと成功事例−」 |
| 参加者 |
学生40名 教職員19名 学外45名 計104名 |
|
|
【概要】
ESCO(Energy Service Company)事業は,省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し,その顧客の省エネルギーメリットの一部を報酬として享受する事業である。ESCO事業者によって,省エネ効果が保証・継続されるものであり,一次エネルギー削減および温暖化ガス排出抑制にもつながることから,世界的に注目されている事業である。大阪府が取り組んでいる民間資金活用型ESCO事業は,既存建築物の設備等について,民間の資金・ノウハウを活用して省エネルギー化改修し,省エネ化による光熱水費の削減分で改修工事にかかる経費を償還し,さらに余剰の光熱水費の削減分より大阪府とESCO事業者の利益を生み出す事業であり,事業の概要ならびにこれまでの事例と省エネの効果を紹介していただいた。
既存の大規模なビルに,コージェネレーションシステム,インバータ照明,インバータ制御のポンプの導入など徹底的な省エネ改修を行うことにより,高い省エネ率,大幅な光熱水費の削減が実現されている事例が紹介された。また,普及促進事業を展開しており,民間ビル,市町村や学校等への導入を視野に入れた今後の事業展開についても紹介された。
本講演では学外からの参加者も非常に多く,ESCO事業に対する関心の高さが伺えた。また,講演後の質疑応答においても活発な議論が交わされ,非常に有意義な講演となった。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成15年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成15年度分)
 vol.4 vol.4
| 日 時 |
平成16年2月9日 12:50 - 14:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気新棟2F 大学院講義室 |
| 講演者 |
三菱電機(株) 先端技術総合研究所 電機システム技術部
グループマネージャー 工学博士 武藤 浩隆氏 |
| 講演題目 |
「電力エネルギー機器における高電圧技術の最新動向」 |
|
|
【概要】
高電圧機器の最近の開発事例として、変圧器、配電機器、発電機などの機器開発について必要な絶縁技術と周辺技術とともに講演された。変圧器、配電機器において大幅な小型化を達成した事例や、電力機器の保守管理に必要な部分放電診断装置の小型化開発の具体的事例を紹介いただいた。
 vol.3 vol.3
| 日 時 |
平成15年11月18日 13:15 - 14:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気新棟2F 大学院講義室 |
| 講演者 |
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所
所長 久間 和生(かずお)氏 |
| 講演題目 |
「産学連携と新事業の構築」 |
| 参加者 |
学生34名 教職員6名 学外3名 計:43名 |
|
|
【概要】
カメラ付携帯電話などに搭載されている「人工網膜LSI」の着想・開発・実用化・事業化を担当した体験をもとに、わが国における新事業構築に向けた産学官連
携のあるべき姿を講演された。開発→実用化段階の「死の谷」、実用化→事業段階の「ダーウインの海」など、新事業構築までに乗り越えるべき課題について具体的に説明いただき、産学連携における研究体制・資金運用・人的交流・期待される大学改革などについて、具体的事例を交えて紹介いただいた。
 vol.2 vol.2
| 日 時 |
平成15年10月9日 14:30 - 16:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気新棟2F 大学院講義室 |
| 講演者 |
九州電力 系統運用部
電力品質管理グループ長 能見 和司 氏
関西電力 電力システム事業本部 調査グループ
チーフマネージャー 乾 俊一 氏 |
| 講演題目 |
「9電力会社の系統の違い」 「電力市場シミュレーション」 |
| 参加者 |
学生29名 教職員4名 外部24名 計57名 |
|
|
【概要】
9電力体制のもと50年が経過した。各電力会社における設備形成や系統運用の方法に関して調査を行い、整理・比較した結果を両氏から紹介いただいた。
また西日本60Hz系統において、火力電源による可変費・コストベースでのLMP(Locational Marginal Pricing)を算定し、混雑発生状況の把握を行うとともに発電設備や送電設備の建設インセンテイブについて評価した結果について紹介いただいた。
また本年欧米で発生した停電の概要についても紹介いただいた。
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成15年7月18日 14:30 - 16:30 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気新棟2F 大学院ゼミ室 |
| 講演者 |
TMT&D社 変電R&Dセンター
センター長 池田 久利 氏 |
| 講演題目 |
「グローバル化する電力研究開発」 |
| 参加者 |
学生5名 教職員4名 外部16名 計25名 |
|
|
【概要】
国内電力需要の伸びが停滞し、また、電力売買の自由化が進展していく中で電力会社の設備投資が縮小している。製造業は生き残りをかけ、国内外で事業展開を図っているが、このような状況において技術動向を把握し、技術動向に適合した将来技術を開発することが電力分野の研究開発に求められている。機器開発については従来の大容量化・小型軽量化技術開発に加えて、今後は環境負荷低減、電力自由化対応、国際標準化に対応した技術開発が必要でありその取り組みの現状を紹介していただいた。
また、期待される将来技術項目として革新材料開発、光応用技術、診断技術、解析技術があり、これらの技術開発を推進するための開放された研究体制、とりわけ大学と企業との連携ならびに研究開発のグローバル化についてその取り組みを紹介いただいた。
 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成14年度分) 寄附講座主催 特別講演会の概要報告(平成14年度分)
 vol.1 vol.1
| 日 時 |
平成15年2月4日 14:30 - 16:20 |
| 場 所 |
九州工業大学工学部 電気新棟2F 大学院講義室 |
| 講演者 |
三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 電機システム技術部
主席技師長 藤井 治久氏
(平成15年4月より 奈良工業高等専門学校教授) |
| 講演題目 |
「電力と環境の静電気技術」 |
| 参加者 |
学生29名 教職員5名 外部19名 計53名 |
|
|
【概要】
GISや変圧器・真空遮断器などの電力機器はコンパクト化による高電界化による固体絶縁物の帯電現象が問題となる。藤井氏は計測技術を駆使した帯電解析技術と抑制・防止技術を研究されており、具体的現象とその研究結果について紹介された。
さらに環境リサイクルへの応用として静電選別技術や究極の電源と見なされている宇宙太陽発電衛星構想における静電気技術についても紹介いただいた。
|