最新パワーエレクトロニクスの進展と国際規格 −EMIとインバータサージ− KIWIS 2004(Kitakyushu International Workshop on Inverter Surge) |
| 2004年10月18日(月) 13:00 - 17:20 | |
| 北九州市立男女共同参画センター「ムーブ」 2F 大ホール | |
| パワーエレクトロニクスとEMIおよびインバータサージの国際規格 | |
| 九州工業大学工学部 寄附講座(九州電力株式会社)電力系統制御工学講座 | |
| 北九州市,電気学会九州支部 | |
| 電気学会,日本電機工業会,IEEE Fukuoka Section, IEEE DEI Fukuoka Chapter |
【プログラム】 (総合司会 匹田政幸 九州工業大学教授)
| 13:00-13:20 | ご挨拶
|
||||||||||
| 13:20-14:20 | 基調講演 「パワーエレクトロニクスの進展とEMI −国際規格と適合性評価の視点から−」 正田 英介(東京理科大学教授,東京大学名誉教授,平成9年度電気学会会長) |
||||||||||
| 14:20-14:40 | (休憩 1F交流広場) | ||||||||||
| 14:40-16:50 | 講演
|
||||||||||
| 16:50-17:20 | パネル討論会 | ||||||||||
| 17:20 | 閉会の辞 |
1. はじめに
2004年10月18日(月)北九州市において,「北九州国際ワークショップ2004:最新パワーエレクトロニクスの進展と国際規格−EMIとインバータサージ−」 が開催され,大学・企業関係者ら約250人が参加した。本ワークショップは九州工業大学工学部寄附講座(九州電力株式会社)が主催したもので,電力から家電まで広く応用されているパワエレ素子の最近の高性能化と応用の現状,それに伴う新たなハード面の課題,そして関連する国際規格活動という総合的なテーマについて,基調講演と5件の技術講演およびパネル討論会があった。基調講演として東京理科大学の正田英介教授より,パワーエレクトロニクス技術の進展・複数の装置間のEMC問題・EMCに関する国際規格の現状について解説いただいた。続いて,インバータ・モータ間のインバータサージ絶縁(注1)の問題について英国・カナダ・韓国・フランス・日本から5件の技術講演があり,最後に講演者全員により総合的な討論が交わされた。
 |
 |
2. 基調講演
はじめに正田先生よりパワーエレクトロニクスの最近の動向のレビューがあり,特に環境調和の観点から全ての電気製品の省エネ化,風力発電などの分散電源と電力系統間の電力制御,高速鉄道,電気自動車など非常に幅広くかつ急速に適用が拡大している現状が紹介された。それに対応してパワーデバイス自体が大容量化・高速化・複合化され,さらにデバイスの統合化技術や冷却技術の発展により小形化が一層進み,大電力用としてIGBTの組み合わせで数kV,数kAの制御が可能となっていること,パワー密度の増大で冷却・EMC技術の重要性が増すこと,将来的にSiCデバイスが期待されていることの説明があった。環境調和型の風力発電・太陽光発電・燃料電池などの分散電源を電力系統に導入するため貯蔵装置とパワエレによる電力変換器を含めた小規模の電力供給ネットワーク 「マイクログリッド」 の開発・試運転が国および地方レベルで検討されている事例が紹介された。
続いて,パワエレ装置からのスイッチングおよび変調によるEMI放射と,外部からの放射EMIの影響があり,協調・両立の必要性が述べられた。IGBT, GTOなど非ラッチ型では伝導性EMIによる誤動作や人体安全の問題にも絡む可能性を指摘された。鉄道や電力系統のように大規模広域のシステム間での電磁障害やパワエレの普及などで電磁障害問題は一層複雑・重要化しており,グローバルな視点での調整すなわち国際規格の重要性が指摘された。EMCの規格化においては複数の機器やシステム間の利害対立即ち,製造者・使用者間,IT機器メーカと電力会社,電力と鉄道会社間さらには輸出・輸入国の相互対立があり,調整機能が非常に大切である。例えばインバータサージではインバータ(SC22G)と回転機(TC2)の2機器間だけの問題であるが,EMCではさらに多数の機器・通信線・電力系統などが関係し,非常に多様な調整が必要である。IECの中においては(比較的低い周波数域の)電磁両立性TC77と(高周波通信の)国際無線障害特別委員会CISPRの2つの委員会が存在し,両委員会がすべての製品群・家電品を対象にEMC規格を出している。一方製品規格側からすると2つの規格の差異について議論が生じ,電磁両立性諮問委員会ACECで調整し,最終的には理事会まで上がることがある。以前ITメーカと電力会社間でのEMC問題について正田先生がタスクフォースの主査を担当し調整に非常にご苦労されたとのことであった。現在,TC77やCISPRが出しているEMC規格は多数あるが,詳細は省略された。
ネットワークの代表例がITS(高度道路交通システム)であるが,国際規格の観点では自動車はISO,ネットワークはIECで調整を要し,さらに人体に対する電磁界の安全性問題はWHOなど規格機関間でも調整が必要である。電力品質についてはEMI以外にもパワーエレクトロニクス機器は電力系統の電圧・周波数への影響やフリッカー発生などの可能性もある。鉄道と電力については,欧州ではEU統合により鉄道が一体化し,それぞれの国の異なる電磁環境に対して一様に対応できる車両でシステム間のEMC問題を克服している。またその他,自然現象・大型装置の運転遮断・テロ手段としての電磁嵐にも言及された。
企業の自己責任制度と政府の規制緩和が進むと,規格に適合しているかを評価する第3者試験機関・認証機関が重要となる。さらに各国間で相互認証するため,国際的に統一する適合性認定機構をISO規格で満たす必要がある。国際規格としては(IECよりも認証の)ISO規格が重要であり,EMCについては61000シリースができている。ヨーロッパではEMCを重視して,EMC指令(Directive)で(自己責任制度ではあるが)半強制的に実施している。試験機関は要請条件とともに電波測定用に大型の試験設備の整備が必要であるが,わが国ではインフラ整備が遅れており今後強化する必要がある。
最後に次世代のパワーエレクトロニクス素子材料として,シリコンカーバイト(SiC)が注目されており,非常に耐圧の高い数十kV, 数kAで低損失のデバイスが期待されている。国際的には欧州産業界のEMC指令に見られる巻き返しも見られるため,わが国が今後国際的取り決めのなかでパワーエレクトロニクス産業を発展させるためには,EMCの強制基準化の範囲制定や評価試験設備の整備など基本的な部分を解決する必要性があることを強調された。最後に質疑のなかで,IECはCENELECとの間にドレスデン協定があり,CENELECで決めたものが自動的にIEC規格になる仕組みがあること,またCISPRのエミッションレベルの低減が必要であれば(日本の)産業界のデータ収集努力と働きかけが必要であることも追加された。
 |
|
<コーヒーブレーク>
|
 |
 |
3. インバータサージ講演会
コーヒブレークをはさんで,次に5件のインバータサージ関連の技術講演に移った。英国のJ.Wheeler博士からインバータサージの発生原理と問題点,さらにIECTC2WG27で取り組んでいるモータ絶縁規格について講演があった。モータはエナメル線を使用する低圧モータとマイカ絶縁を使用する高圧モータに大別されるが,インバータサージが進入すると低圧ではターン間の不平等電圧分担,高圧では非線形電界緩和の発熱問題などがあることが解説された。現在同氏が主査をしているWG27では13カ国18名の委員でモータ絶縁評価に関する規格を作成中である。
続いて,カナダIRIS社のG.Stone博士より欧米におけるインバータ駆動モータの具体的事故例(690V級)の写真紹介およびその破壊原因として部分放電(注2)現象の説明があった。例えば立ち上がり時間50nsのサージがモータに進入した場合コイルの電圧分担率が不平等となり,第一ターン間に大半の電圧がかかり,付近の空気ギャップで部分放電が発生する。部分放電は従来1MHz以下の周波数で検出されていたが,インバータサージ電圧自体がそれ以上の周波数成分を有しており,部分放電検出にはさらに高周波領域での検出が必要である。モータ絶縁の特性として部分放電開始電圧(PDIV)が重要なパラメータであり,GEとの一連の共同実験データについて解説が行われた。
次に韓国電気研究所(KERI)のY.J.Kim博士から,韓国でのインバータサージ絶縁の研究紹介があった。1998年当時低圧モータで絶縁事故が相次いで発生し,LG,Hyundaiなどの複数の韓国企業からの要請により,KERIでは事故原因解明と対策に関する研究を実施した。業界からはモータ絶縁の標準化の要望があり,さきほどの講演にもあった部分放電開始電圧(PDIV)計測を,絶縁補強も含めた多数の試料について詳細な検討を行った。KERI内のシールドルームで1pCレベルの高感度計測を実施し,真空含浸などの絶縁補強効果を整理・提示することができた。
続いてフランスのT.Lebey博士からは国立科学研究センタ(CRS)における15年間の可変速駆動(ASD)モータ内の電圧波形研究およびインバータの構造・絶縁設計研究の紹介があった。モータ内の過渡的な電圧分担と部分放電現象の解明によって長寿命エナメル線の開発に寄与できた。現在主に半導体及びモジュール内部構造の最適化を研究しており,パッシベーション技術・基板・統合化技術などを担当している。次世代のSiCについても素子内部の端子・電界緩和・保護回路・パッシベーションなどを材料も含めシミュレーションなどで解析している。高圧素子の故障の原因である部分放電の抑制についてもジェルを含む統合化技術として検討しているとのことである。
最後に九州工業大学寄附講座木村客員教授より日本のインバータサージ研究の現状紹介を行った。わが国では調査活動や国際規格活動に早くから取り組んでおり,現在も企業レベルでの研究は活発であるが,公表データが少ないことが紹介された。具体的データとして,名古屋大学大久保研究室と九州工業大学匹田研究室の最新の研究成果が紹介された。
 |
 |
 |
 |
 |
|
4. パネル討論
講演者全員によるパネル討論会が行われ,木村客員教授が司会を担当した。開催の前週に司会者が個人的に体験した上海の高速磁気浮上リニアモータカーの写真が紹介され,まず正田先生のリニアモータカーに関する世界的動向解説からスタートした。(以下敬称略)
正田: 上海で高速の400km/h級が実用化し,低速型では来年名古屋万博用に200km/hが運転される予定であるが,構造的には高速と低速では異なる。低速は従来駆動に近いが,高速はロングステータ駆動と呼ばれ,駆動部が地上にあり,モータ部品のみ車体に搭載するため,モータよりも給電用パワーケーブルの容量が問題となる。中国の場合モータよりもケーブルでの故障が問題になるようだ。欧米で高速鉄道はいろいろ検討されたが,具体的計画はミュンヘン空港および日本の山梨実験線などのみである。
次に今後のパワードライブ市場の中心は電気自動車であり,モータとコンバータが一体化した小形車が短距離用に広まるのではないか。コンパクト化する際に絶縁技術も課題となろう。コミュニティーベースの小型車が中心となると予想する。ケーブルのない,コンバータ一体型のモータではインバータサージについては問題ないのではないか。
司会: 一体型ではオーバシュートは生じないが,電圧自体はプリウスのように高電圧化していくのではないか。
正田: そう思わない。電気自動車は小形のものに限定されるのではないか。理由のひとつは安全性で400V以上では運転上問題が生じる。環境にやさしいコミュニティスペースでの利用が経産省での効率的エネルギー活用で議論された予想である。
司会: 環境にやさしい電気自動車がますます注目されいるが,環境問題に関心の高い欧州での電気自動車への関心はどうか?
レベイ: フランスにおいてはホンダとトヨタのハイブリッドカーの関心が高く,ルノーなども検討中である。
司会: 英国ではどうか。
フイーラ: 英国では以前バーミンガム空港で磁気浮上リニアカーが運転されたが,残念ながら数年後モータの焼損事故があり断念した。
司会: 日本では絶縁事故を経験し企業内部で検討されたデータの公表例は非常に少ない。北米では事故率の分析・データの公表などについてどうか?
ストーン: インバータ駆動モータは非常に増加しているが,事故率はまだそれほど大きくない。また文献での過電圧サージ値は最悪の回路条件での計算結果で,我々が多数の稼動しているモータを実測した結果ではサージ値が大きいものは少ない。インバータ直結型モータではオーバシュート問題はなくなるが,ケーブルの制動効果がない。電気自動車においては低圧モータの小形化要求が強いため高電界化した場合,立上りの速い直流高電圧の進入は依然絶縁上問題である。高圧PWM駆動モータも今後増加すると考えられる。コイルエンド部の電界緩和の発熱問題がある。絶縁上の問題は多くの企業で検討しているが,通常データはほとんど公表されておらず,先ほどのフイーラ氏のデータははじめて見た。
正田: 部分放電も重要であるが,製品寿命を考えるべきではないか。米国コロラド大学での研究でも発熱による寿命の低減を確認しているが実機ではクレームまで至っていない。一般にパワエレ機器,例えば高速列車は通常製品寿命が非常に短く,顧客も短期間使用を考えている。モータ設計で30年としても,実際は7-10年程度で交換されており,新幹線でも15年である。
金: 韓国でのハイブリッドカーと高速鉄道にコメントしたい。ハイブリッドカーの高電圧化と同様,韓国自動車の(駆動系でない)電気系統も高圧化する。韓国は90年代中ごろソウル・プサン間を時速300km/hで結ぶ高速鉄道を検討し,ドイツ・フランス・日本の方式を検討した。フランスは旧式のシンクロナスモータを提案したがノイズが大きくラインフィルタが必要だった。その後韓国では新たに独自の高速鉄道開発プロジェクトを1998年から開始した。目標時速350kmでPWM駆動を採用し,ポリゾラと共同で高電圧絶縁を開発し,コンパクトなモジュールとした。当時我々は素子はIGBTでなくIGCTを採用し,スイッチング周波数は500Hzとした。フィールド試験を実施しており,昨年これまでの試験報告が出たが,IGBT・IGCTとも同様の技術課題があるように思われる。
レベイ: フランス技術へのクレームがあったので反撃したい。われわれは古い考え方を改め,アルストームと大学で共同の研究所PEARLを作り,日本製と異なるフランス独自のPWMパワーモジュール構造を開発した。バンプフリップチップ実装技術により2面冷却を可能とし一相分32台をコンパクトに搭載したモジュールで,電車に搭載され順調に稼動している。これはフランスの産学連携での開発の一例である。この新実装モジュールはいずれ韓国に輸出したい。
司会: 最後に日本における産学連携や戦略について,正田先生からご見解をお願いしたい。
正田: まず連携といっても材料・パワエレメーカ・応用エンジニア間の共同作業がある。SiC開発を例にとって見ると,材料特性が従来と非常に異なり200℃以上で運転可能なので,応用製品は従来と大きく異なり,統合化も異なる。NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)ではグループを作り,製品応用のための多様な解析ツールなどが必要になる。電界分布解析ソフトや集積構造というテストベンチが必要で,このような個々の技術の相互協力は国・大学・業界間で一層重要であると思われる。国際標準化については経産省に属する問題で,産業界からより働きかけ国の資金を通じて活発化する必要があるが,産業界からの働きかけが少ない。2年前に日本の国際規格に関する戦略について報告書を発行しておりご参考にしていただきたい。
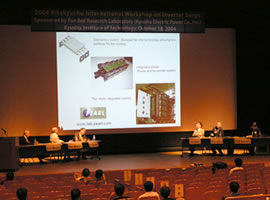 |
 |
5. あとがき
今回のワークショップは,当初IECTC98無錫会議に合わせインバータサージ絶縁に限定する予定であったが,多くの方のアドバイス・ご協力でより広い視野で最新のパワーエレクトロニクスのハード的課題に関する解説・最新動向のご講演と質疑討議することができた。司会の不手際で一部議論がかみ合わない部分もあったが,この分野の課題が総合的に理解されたと思われる。この種のイベントは東京地区でよく開催されているが,パワー半導体や自動車関連の設備投資が活発な北部九州において,関係技術に関する情報発信ができた意義は大きいものがあると考えられる。今後機会があれば再度の開催を企画していきたい。
注1: インバータサージ: インバータ駆動モータにおいて,パワー素子の立上り時間が短くケーブル長が長い場合に発生する急峻インパルス電圧。インバータ・ケーブル・モータのサージインピーダンスの違いにより,直流電圧の2倍のピーク値がPWMの各方形波の波頭と波尾に繰り返し発生するため,モータ絶縁に対する新しい電気ストレスとして研究が進められている。IGBTなどのパワエレ素子の高電圧化・高速化に伴い,絶縁事故率の増加が懸念されるため適切な評価と対策が検討されている。
注2: 部分放電(PD): 機器内の気体部分の局所的放電。交流電圧に対して継続的に発生し,絶縁劣化が進行すると絶縁寿命が減少する。放電パルス立ち上がり時間は極めて短く信号も弱いため検出方法が研究開発されている。
 |
(左から)松本客員教授,匹田教授,木村客員教授,諸岡所長,Stone博士,正田教授, 下村学長,Wheeler客員教授,Lebey博士,Kim博士,高田課長,佐藤局長 |
 |
(左から)正田教授,Lebey博士,Wheeler客員教授,Kim博士,Stone博士 |